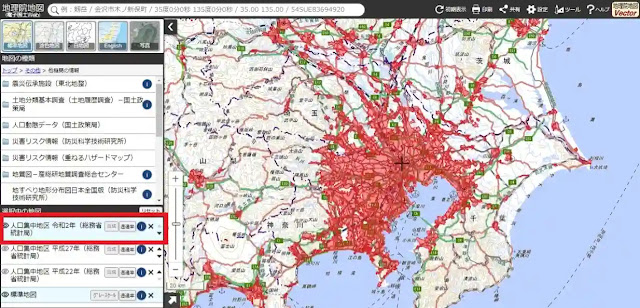一般的なレーダーの仕組み ATCの話6
2025年9月29日
2025年9月30日
現在の一般的なレーダーの仕組み
レーダーは、電波を利用して物体の距離(測距)、方向(方位角および仰角)、および動径速度を測定するシステムであり、無線を用いた測位技術のひとつです。この技術は、航空機、船舶、宇宙船、誘導ミサイル、自動車などの検出および追跡に用いられるほか、気象の観測や地形の地図作成など、さまざまな分野で広く利用されています。
レーダーは、マイクロ波という波長数ミリから数十センチの高周波電磁波を用いて、目標物の距離、方位角・仰角、さらには動径速度を測定するシステムです。航空機や船舶、宇宙船、誘導ミサイル、自動車の検出・追跡のみならず、気象現象の観測や地形の地図作成など、幅広い無線測位用途に活用されています。
レーダーは第二次世界大戦の前後に、複数の国で軍事目的のために秘密裏に開発されました。主要な技術的進歩はイギリスのキャビティマグネトロン[cavity magnetron](空洞磁電管)であり、これによって1メートル未満の分解能を持つ比較的小型のシステムが実現可能となりました。「RADAR」という用語は1940年にアメリカ海軍によって「RAdio Detection And Ranging」(電波検知および測距)の頭字語として作られました。その後、「radar」は英語やその他の言語において一般名詞となり、大文字表記は使われなくなりました。日本語では電波探信儀、略して電探と呼ばれていました。マグネトロンは発振用真空管の一種で、磁電管(じでんかん)とも呼ばれ、電磁波の一種である強力なマイクロ波を発生します。これはレーダーや電子レンジに使われています。
レーダーの原理は、山に向かって声を出すと反響が返ってくる「山びこ」の現象に例えることができます。ただしレーダーでは音波ではなく、主に波長が数ミリメートルから数十センチメートルのマイクロ波と呼ばれる高周波の電磁波が用いられます。マイクロ波を特定の方向に発射し、その進行方向に物体(物標)が存在すると、電波がその表面で反射されます。反射された電波の一部は再びレーダーのアンテナに戻ってきます。この往復にかかる時間を測定し、電波の伝搬速度である光速を用いることで、レーダーは物体までの距離を算出します。また、アンテナの向きを基にすることで、物体の方位を特定することもできます。連続的に変化する信号のドップラーシフトを解析することで動径速度も検出できます。
レーダーシステムは、電磁波を発生させる送信機、電波を空間に放射する送信アンテナ、反射波を受け取る受信アンテナ(多くの場合は送受信兼用のアンテナ)、そして受信した信号を解析して物体の特性を決定する受信機および信号処理装置から構成されています。こうして取得された物体の距離や方向の情報は、ディスプレイに映像として表示されます。
とりわけ多くのレーダー装置では、PPI(Plan Position Indicator:平面位置表示器)と呼ばれる表示形式が用いられています。これは、レーダーを中心とした同心円状の画面上に、物体の方位と距離に応じた位置をリアルタイムで表示する方式です。PPI表示は、航空機や船舶の航行支援、あるいは気象観測において、情報を直感的かつ視覚的に把握するのに適しているため、広く採用されています。レーダーが捉える対象である「物標」には、動かない対象である建物や地形だけでなく、移動している飛行機、船舶、自動車なども含まれます。さらに、雨雲や嵐といった自然現象もレーダーによって観測可能な物標に含まれます。レーダーが使用するマイクロ波は波長が短いため、距離や方位を高精度に測定できるという利点があります。
このような特徴を生かして、現在ではさまざまな種類のレーダーが実用化され、その用途は非常に多岐にわたっています。船舶の航行支援や海洋レーダーによる地標や他の船舶の位置特定、気象観測に使われる気象レーダー、航空機の離着陸や飛行を監視する航空管制レーダーなどが代表的です。また、航空および陸上交通管制、航空機の衝突防止システム、海洋監視システムにも広く活用されています。軍事面では防空システム、対ミサイルシステム、誘導ミサイルの目標位置特定システムなどに利用されています。科学技術分野では地面の下を観測する地中レーダー、人工衛星からのレーダーリモートセンシング、宇宙空間監視および会合システムにも応用されています。さらに、日常生活に近い用途として、道路交通における速度違反の取締りに使われるスピード測定器や、野球における投球速度の計測(いわゆるスピードガン)にも、レーダー技術が応用されています。
さらに最先端のレーダーではデジタル信号処理や機械学習技術を導入し、雑音環境下でも微小な反射信号を高精度に検出できるようになりました。無人運転車の開発が進む中では、周囲環境のリアルタイム監視や衝突防止支援のため、レーダーと併せて赤外線レーザーを用いるライダー(LiDAR : Light Detection And Ranging)など、他周波数帯を使った類似技術も注目を集めています。
レーダーの応用
レーダーの情報には、レーダーから物体への方位と距離(つまり位置)が含まれます。そのため、位置特定が重要な多くの異なる分野で使用されています。レーダーの最初の用途は軍事目的であり、空中、地上、海上の目標を特定するためのものでした。これは後に民生分野で、航空機、船舶、自動車への応用へと発展しました。
航空分野では、レーダー装置は多種多様な用途で重要な役割を果たしています。航空機にレーダー装置を装備することで、機体の経路内または経路に接近する航空機や他の障害物を警告し、気象情報を表示し、正確な高度情報を提供できます。
民間航空での気象レーダーの実用化は第二次世界大戦後の1940年代後半から始まりました。現代の航空機に搭載されている気象レーダーは、前方の降水強度や乱気流を検出し、パイロットが危険な気象状況を回避するための重要なツールとなっています。特に最新のドップラーレーダーシステムは、風の流れを可視化することで、マイクロバーストやウインドシアなどの危険な現象を早期に検知できます。
空港の航空管制では、レーダー支援地上管制進入システム(GCA)を活用しています。
GCA (Ground Controlled Approach: 地上管制進入システム) を備えた空港では、滑走路への定められた進入経路に航空機を維持するため、精密進入レーダー画面上で航空機の位置を観察するオペレーターが、パイロットに無線を通じて着陸指示を与えます。
現代では、ILS (Instrument Landing System: 計器着陸システム) やMLS (Microwave Landing System: マイクロ波着陸システム) などの自動化されたシステムも広く使用されています。
GCA (Ground Controlled Approach: 地上管制進入システム) を備えた空港では、滑走路への定められた進入経路に航空機を維持するため、精密進入レーダー画面上で航空機の位置を観察するオペレーターが、パイロットに無線を通じて着陸指示を与えます。
現代では、ILS (Instrument Landing System: 計器着陸システム) やMLS (Microwave Landing System: マイクロ波着陸システム) などの自動化されたシステムも広く使用されています。
また、航空交通管理のための一次監視レーダー(PSR)や二次監視レーダー(SSR)は、空域内のすべての航空機を追跡するために不可欠なインフラとなっています。
軍用航空機の分野では、戦闘機は通常、空対空目標捕捉レーダーを装備しており、敵機を探知・追跡します。最新のAESA(アクティブ電子走査アレイ)レーダーは、複数の目標を同時に追跡し、高解像度のイメージングも可能にしています。さらに、大型の特殊軍用機(AWACS (Airborne Warning And Control System: 空中警戒管制システム) 等)は強力なレーダーを搭載し、広範囲の航空交通を監視し、戦闘機を目標に向けて誘導します。
軍用航空機の分野では、戦闘機は通常、空対空目標捕捉レーダーを装備しており、敵機を探知・追跡します。最新のAESA(アクティブ電子走査アレイ)レーダーは、複数の目標を同時に追跡し、高解像度のイメージングも可能にしています。さらに、大型の特殊軍用機(AWACS (Airborne Warning And Control System: 空中警戒管制システム) 等)は強力なレーダーを搭載し、広範囲の航空交通を監視し、戦闘機を目標に向けて誘導します。
近年急速に発展している分野として、無人航空機(ドローン)検出レーダーがあります。空港周辺や重要インフラ施設では、従来のレーダーでは検出が困難な小型ドローンを探知するための特殊なレーダーシステムが導入されています。
また、バードストライク(鳥の衝突)防止のための鳥類検出レーダーも重要な応用分野です。空港周辺の鳥群の動きをリアルタイムで監視し、危険が予測される場合に警告を発します。これらのシステムは通常、Xバンド(8-12 GHz) や Sバンド(2-4 GHz)の周波数を使用し、3Dで鳥の動きを追跡できるよう設計されています。バードストライクは航空安全上の重大なリスク要因であり、これらのレーダーシステムにより年間数百件の潜在的な事故が防止されていると推定されています。
さらに、最新のヘリコプター安全技術として、HTAWS(Helicopter Terrain Awareness and Warning System)にレーダー高度計を組み合わせたシステムが普及しています。これにより、視界不良条件下での地形衝突や障害物との接触リスクが大幅に軽減されています。
航空分野におけるレーダー技術は、飛行安全性の向上、効率的な空域管理、気象ハザードの回避など、多岐にわたる目的で活用されています。
海洋レーダーは、他の船舶との衝突を防ぐため、船舶の方位と距離を測定して航行を支援し、海岸や島、ブイ、灯台などの固定基準点との関係から自船の位置を特定するために使用されます。港内や入江では、VTS (Vessel Traffic Service: 船舶交通サービス) レーダーシステムが、混雑した水域における船舶の移動を監視・規制するために使用されます。
気象関連では、降水量と風を監視するためにドップラーレーダーを使用します。これは短期天気予報や、雷雨、竜巻、冬の暴風雪、降水の種類などの激しい気象現象を監視する主要なツールとなっています。地質学者は、地球の地殻の組成を地図化するために、特殊なGPR (Ground Penetrating Radar: 地中レーダー)を使用します。
警察では、道路上の車両速度を監視するために速度レーダー(スピードガン)を使用します。自動車レーダーは、適応クルーズコントロールと緊急ブレーキシステムに使用され、停止中の路側物を無視し、移動物体を検知して他の車両との衝突を防ぎます。現代の自動車では、77GHzや24GHzのミリ波レーダーが自動運転技術の重要な要素となっており、LiDAR (Light Detection And Ranging: ライダー)や各種カメラと併用されています。ITS (Intelligent Transport Systems: 高度道路交通システム) の一環として、SVD (Stopped Vehicle Detection: 停止車両検出) レーダーが路側の固定位置に設置され、移動物体を無視して立ち往生した車両、障害物、がれき などを検出します。
小型レーダーシステムは、人間の動きを検出するために幅広く応用されています。近年の半導体技術とデジタル信号処理の進歩により、ミリ波レーダー(24GHz、60GHz、77GHzなど)、超広帯域(UWB)レーダー、FMCW(周波数変調連続波)レーダーなどの小型化・低コスト化が実現し、様々な民生用途が急速に広がっています。
睡眠モニタリングにおいては、60GHz帯の信号を用いて胸部の0.1〜0.5mm程度の微細な動きを検出する技術により、非接触で呼吸パターンを監視できます。GoogleのNestシリーズに搭載されたSoli技術などで、実用化されています。また、コンピューター操作のための手や指のジェスチャー検出も進化しており、Google Pixel 4以降のスマートフォンに搭載されたSoliセンサーでは、電話の応答拒否や音楽再生のコントロールが可能になっています。
スマートホームでの応用も多岐にわたります。低電力24GHzレーダーセンサーを使用した自動ドア開閉や照明制御が一般化しており、Bosch社 BMI270センサー搭載のスマートサーモスタットなどが市場に出回っています。セキュリティ分野では、動物や風で動く植物と人間を区別できる高度なアルゴリズムを搭載したシステムが登場しています。これらは特にプライバシー保護の観点から、カメラと異なり詳細な個人情報(画像)を取得せずに監視可能な点が評価され、高齢者見守りシステムなどで採用が進んでいます。
医療分野での応用も急速に発展しています。非接触バイタルサイン監視では、呼吸数、心拍数、体動などの生体情報を取得できる機器が、病院のベッドサイドモニタリングや乳幼児の突然死症候群予防に活用されています。さらに認知症患者や高齢者の見守りでは、非接触患者モニタリングシステムにより、夜間徘徊検知やトイレ使用パターン分析などが可能になっています。
最新の技術動向としては、TI社 AWR6843やNXP社 TEF810Xなどの1チップ統合型レーダーモジュールの登場により、従来の10分の1以下(数百mW)の消費電力を実現しており、AI/機械学習との統合により、レーダー信号から95%以上の認識率でジェスチャーを識別したり、異常行動パターンを自動検出したりする機能も実用化されています。今後は、スマートウォッチへの搭載や、MITメディアラボで研究が進む衣類に統合された柔軟なレーダーセンサー、自動車内の乗員検知システムなど、さらなる応用領域の拡大が期待されています。
これらの小型レーダー技術は、プライバシーを保護しながら人間の生活をサポートする次世代センシング技術として、特に非接触・非視覚的な監視が求められる場面で急速に普及が進んでいます。
レーダーの原理
レーダー信号
レーダーシステムは、特定の方向に電波(レーダー信号)を発信する送信機を持ちます。これらの信号は通常300MHz〜30GHz(波長1m〜1cm)の周波数範囲で運用され、用途によって最適な周波数帯が選択されます。送信された電波が物体に接触すると、通常、様々な方向に反射または散乱され、一部は吸収されて対象物に浸透します。レーダー信号は、大きな電気伝導性を持つ材料、つまりほとんどの金属、海水、湿った地面で特に良く反射します。これにより、特定の場合にレーダー高度計の使用が可能になります。
レーダー受信機に向かって反射されるレーダー信号が、レーダー検出を可能にする重要な信号です。対象物が送信機に向かって、または送信機から離れて移動している場合、ドップラー効果により電波の周波数にわずかな変化が生じます。この周波数変化を利用することで、移動物体の速度を正確に測定することができます。
レーダー受信機は、通常は(一部の例外を除いて)送信機と同じ場所に配置されています。受信アンテナが捉えるレーダー反射波は、通常非常に微弱です。この弱い信号は電子増幅器によって強化されます。有用なレーダー信号を回復するために、パルス圧縮、コヒーレント積分、MTI(Moving Target Indication)などのさらに洗練された信号処理方法も使用されます。
電波が通過する媒質による電波の弱い吸収により、レーダー装置は比較的長距離で物体を検出できます。これは、可視光、赤外線、紫外線などの他の電磁波長が強く減衰する距離においても可能です。霧、雲、雨、降雪、みぞれなどの気象現象は可視光を遮断しますが、通常、電波に対して透明です。水蒸気、雨粒、または大気ガス(特に酸素)によって吸収または散乱される特定の無線周波数は、それらの検出が意図されている場合を除き、レーダー設計の際に回避されます。
照 射
レーダーは、太陽や月の光、または赤外線(熱)などの対象物自体が発する電磁波ではなく、独自の送信波に依存しています。人間の目や光学カメラには見えない人工の電波を対象物に向けて送信するこのプロセスを「照射」と呼びます。
反 射
電磁波が異なる誘電率または磁性率を持つ別の物質に遭遇すると、波は物質間の境界で反射または散乱します。これは、空気中や真空中の固体物体、または物体とその周囲の間の原子密度の大きな変化が、通常、レーダー波(電波)を物体の表面から散乱させることを意味します。これは特に金属や炭素繊維などの電気伝導性の高い材料に当てはまり、レーダーが航空機や船舶の検出に適している理由となっています。
軍用車両には、レーダー反射を減らすために、抵抗性や磁性物質を含むレーダー吸収材(RAM : Radar Absorbent Material)が使用されます。現代のステルス技術は、角度の最適化だけでなく、レーダー吸収材の使用や表面形状の最適化など複合的なアプローチを採用しています。
これは、夜間に視認されないよう暗色塗装を施すことの電波版と言えるでしょう。
これは、夜間に視認されないよう暗色塗装を施すことの電波版と言えるでしょう。
レーダー波の散乱は、電波の波長(周波数)と対象物の形状に応じて様々な形で生じます。
波長が対象物のサイズよりもはるかに短い場合、波は鏡で光が反射するのと同様に跳ね返ります。波長が対象物のサイズよりもはるかに長い場合、十分な反射が得られず対象物を検出できない可能性があります。
波長が対象物のサイズよりも大きい場合の散乱現象はレイリー散乱と呼ばれ、地球の青い空と赤い夕焼けを生み出す効果でもあります。
波長と対象物のサイズが同程度である場合、共振現象が生じる可能性があります。初期のレーダーは対象物よりもはるかに長い波長を使用していたため、曖昧な信号を受信していましたが、多くの現代のシステムはより短い波長(数センチメートル以下)を使用し、パンの大きさほどの小さな物体を画像化できます。
波長と対象物のサイズが同程度である場合、共振現象が生じる可能性があります。初期のレーダーは対象物よりもはるかに長い波長を使用していたため、曖昧な信号を受信していましたが、多くの現代のシステムはより短い波長(数センチメートル以下)を使用し、パンの大きさほどの小さな物体を画像化できます。
波長が短い電波は、丸いガラス片からの光の反射と同様に、曲面や角から反射します。短波長で最も反射の強い対象は、反射面間に90°の角度を持つものです。コーナー反射器は、立方体の内側の角のように、3つの平面が交わる構造を持ちます。この構造は、開口部から入る波を直接送信元に反射します。これらは、検出が困難な物体をより検出しやすくするためのレーダー反射器としてよく使用されます。例えば、ボートのコーナー反射器は、衝突を避けたり、救助時に検出されやすくしたりします。
同様の理由で、検出を避けようとする物体は、内側の角や検出される可能性の高い方向に垂直な表面やエッジを持たないため、「奇妙な」外観のステルス航空機となります。これらの予防措置は、特に長波長では回折のため、反射を完全に排除するわけではありません。
半波長の長さの導電性材料の線や帯(チャフなど)は非常に反射性が高いですが、散乱エネルギーを送信元に向けて直接戻すことはありません。チャフは主に軍用機が敵のレーダーを妨害したり、偽の目標を作り出したりするために使用されます。
物体が電波を反射または散乱する程度は、そのレーダー反射断面積(RCS:radar cross-section)と呼ばれます。RCSは通常、平方メートル(m²)の単位で表され、物体の形状、材質、電波の波長、入射角によって大きく変化します。例えば、同じ航空機でも正面からのRCSと側面からのRCSは大きく異なる場合があります。
レーダー距離方程式
基本方程式
レーダーと対象物との関係は、レーダー距離方程式(radar range equation)によって表されます。
これはレーダーの受信電力(受信機に到達する信号エネルギー)を、レーダーの送信出力とアンテナ利得、レーダー反射断面積、送信波長(周波数)、および目標までの距離の関数として計算するものです。
受信アンテナに返ってくる電力 Pr [W] は、次の方程式で計算できます:
これはレーダーの受信電力(受信機に到達する信号エネルギー)を、レーダーの送信出力とアンテナ利得、レーダー反射断面積、送信波長(周波数)、および目標までの距離の関数として計算するものです。
受信アンテナに返ってくる電力 Pr [W] は、次の方程式で計算できます:
Pr = Pt・Gt・Ar・σ・F / (4π)²・Rt²・Rr²
ここでは:
Pt [W] : 送信機の電力
Gt [dBi] : 送信アンテナの利得
Ar [m²] : 受信アンテナの実効開口(面積)。これは Gr × λ² / (4π) として表現できます
λ [m] : 送信波長
Gr [dBi] : 受信アンテナの利得
σ [m²] : 対象物のレーダー反射断面積、または散乱係数
F : パターン伝搬係数(電波伝搬環境による影響を表す係数)
Rt [m] : 送信機から対象までの距離
Rr [m] : 対象から受信機までの距離
モノスタティックレーダーの場合
送信機と受信機が同じ場所にある『モノスタティックレーダー』の一般的な場合では、
Rt = Rr = R となり、Rt² × Rr² は R⁴ に置き換えられます。これにより:
Rt = Rr = R となり、Rt² × Rr² は R⁴ に置き換えられます。これにより:
Pr = Pt・Gt・Ar・σ・F / (4π)²・R⁴
この方程式は、受信電力が距離の4乗に比例して減少することを示し、遠方の対象物からの受信電力が距離に応じて急激に減少することを意味します。
拡張レーダー方程式とSNR
実用的なレーダーシステムでは、信号対雑音比(SNR)を考慮した拡張レーダー方程式が重要です:
SNR = (Pt・Gt・Gr・λ²・σ・F) / ((4π)³・R⁴・k・Ts・B)
ここでは:
k [J/K] : ボルツマン定数(1.38 × 10⁻²³ J/K)
Ts [K] : システム雑音温度
B [Hz] : 受信機の帯域幅
実世界の影響要素
上記の方程式において F = 1 は、干渉のない真空中での伝搬を簡略化した理想的な状態を表します。
実際の環境では:
- 伝搬係数は、多重経路効果と遮蔽の影響を考慮し、環境の詳細に依存します
- 実世界の状況では、大気による減衰や経路損失の影響も考慮する必要があります
- パルス圧縮技術を用いることで、高い平均電力を維持しながら距離分解能を向上させることができます
パルス積分とフィルタリング
追加のフィルタリングとパルス積分は、パルスドップラーレーダーの性能のためにレーダー方程式を修正し、検出範囲を増加させ、必要送信電力を減少させることができます。複数のパルスからの情報を統合することで、単一パルスよりも優れた検出性能を実現できます。
ドップラー効果
基本原理
ドップラー効果は、反射体とレーダー間の相対運動による周波数シフトを引き起こします。これは、波長の変化として観測され、対象物の速度情報を提供します。
アクティブレーダーのドップラー周波数シフト
アクティブレーダー(信号を送信し、反射を受信するレーダー)のドップラー周波数シフトは次のとおりです:
FD = 2・FT・(VR / C)
ここでは:
FD [Hz] : ドップラー周波数
FT [Hz] : 送信周波数
VR [m/s] : 放射速度(レーダービーム方向の速度成分)
C [m/s] : 光速(約3×10⁸ m/s)
パッシブレーダーのドップラー周波数シフト
パッシブレーダー(対象自体が発する信号を受信するシステム)は、電子対抗手段と電波天文学に適用され、次の式で表されます:
FD = FT・(VR / C)
ドップラー効果の幾何学的考察
ドップラー効果に関係するのは対象物の速度のうち、レーダービーム方向の速度成分(放射速度)のみです:
- 対象物がレーダービームに対して直角に移動している場合、放射速度はゼロとなり、ドップラーシフトは発生しません
- レーダービームに平行に移動する物体は、最大のドップラー周波数シフトを生成します
パルスドップラーレーダーの曖昧性
送信周波数(FT)がパルス化され、パルス繰り返し周波数(FR [Hz])を使用する場合、結果の周波数スペクトルには、FT の上下に FR の距離で調和周波数が含まれます。
ドップラー測定は、ドップラー周波数シフトが FR の半分未満である場合にのみ、曖昧さなく測定できます(ナイキスト基準):
|FD| < FR / 2
アクティブレーダーの式を代入すると:
|2・FT・(VR / C)| < FR / 2
これを VR について解くと:
|VR| < (FR・C) / (4・FT)
実 例
パルス率2 kHz(FR = 2000 Hz)で送信周波数1 GHz(FT = 10⁹ Hz)のドップラー気象レーダーの場合:
最大測定可能速度 = (2000 × 3×10⁸) / (4 × 10⁹) = 150 m/s(約340 mph)
このレーダーは、150 m/sまでの天候や目標の速度を信頼性高く測定できますが、1,000 m/s(約2,200 mph)で移動する高速航空機の放射速度を一意に決定することはできません。
ドップラー効果の応用例
- 気象レーダー:降水の動きと強度を測定
- 軍用機レーダー:移動目標検出と追跡
- 警察の速度測定レーダー:車両速度の取締りと測定
- 移動目標指示(MTI)システム:静止背景から移動物体を分離
- 半アクティブレーダー誘導:誘導ミサイルにおける目標追尾
- レーダー天文学:天体の観測と分析
ドップラー効果の利用により、検出プロセス中に対象の速度に関する情報が得られるだけでなく、大きな静止物体や低速移動物体が近くに存在する環境でも、小さな移動物体を検出することが可能になります。
偏 波
すべての電磁放射において、電界は伝搬方向に対して垂直です。偏波とは、電界ベクトルの向きの変化パターンを表します。送信レーダー信号の偏波は、異なる効果を得るために制御できます。レーダーは、さまざまな種類の反射を検出するために、水平偏波、垂直偏波、直線偏波、円偏波を使用します。例えば、円偏波は雨によって引き起こされる干渉を最小限に抑えるために使用されます。直線偏波で反射してくる電波は、通常、金属表面の存在を示します。ランダム偏波で反射してくる電波は、通常、岩や土壌のような不規則または粗い表面の存在を示し、ナビゲーションレーダーで観測されます。
制限要因
ビーム経路と範囲
レーダービームは真空中では直線的に進みますが、空気の屈折率変化によって、やや湾曲した経路を進みます。これは『レーダー地平線』と呼ばれる現象で、大気中の屈折率勾配によって電波が地球の曲率に沿って湾曲することを指します。これにより、幾何学的な地平線よりも遠くまで電波が届きます。
ビームが地表に平行に送信されても、地球の曲率によってビームは地表から離れていきます。さらに、信号はビームが横断する媒体によって減衰し、ビームは拡散します。
ビームが地表に平行に送信されても、地球の曲率によってビームは地表から離れていきます。さらに、信号はビームが横断する媒体によって減衰し、ビームは拡散します。
従来のレーダーの最大範囲は、いくつかの要因によって制限されます:
- 地上高に依存する直線視界。直線視界がない場合、ビームの経路は遮断されます。
- パルス繰り返し周波数によって決定される最大非曖昧範囲。最大非曖昧範囲とは、次のパルスが送信される前に電波が往復できる最大距離であり、数式では c/(2×PRF)(cは光速、PRFはパルス繰り返し周波数)で表されます。
- レーダー方程式で計算される、レーダーの感度と反射してくる信号の電力。この要素には、環境条件や対象物のサイズ(またはレーダー断面積)などの要因が含まれます。
ノイズ
信号ノイズとは、すべての電子部品内で発生する信号内のランダムな変動の内部的要因です。
反射信号は距離が増加するにつれて急速に減衰するため、ノイズはレーダー範囲に制限を導入します。ノイズフロアと信号対雑音比は、レーダーの検出距離性能に影響する2つの異なる評価指標です。あまりにも遠くにある反射体は、ノイズフロアを超えるには十分に小さい信号を生成するため、検出できません。検出するためには、信号がノイズフロアを超え、かつ十分な信号対雑音比を持つ必要があります。
ノイズは通常、レーダー受信機で受信される所望のエコー信号に重畳されるランダムな変動として現れます。所望の信号の電力が低いほど、ノイズから識別することが困難になります。ノイズ指数は、理想的な受信機と比較した受信機によって生成されるノイズの尺度であり、これを最小限に抑える必要があります。
ショットノイズは、不連続部を通過する電子によって生成され、すべての検出器で発生します。ショットノイズは、ほとんどの受信機で支配的な源です。増幅デバイスを通過する電子によって引き起こされるフリッカーノイズもあります。ヘテロダイン処理は主に信号処理の柔軟性を高めるために使用されます。ヘテロダイン処理のもう一つの利点は、相対帯域幅(または比帯域幅)に対して、瞬時帯域幅が周波数に対して直線的に増加することで、これにより距離分解能が向上します。ヘテロダイン(ダウンコンバージョン)レーダーシステムの1つの注目すべき例外は、超広帯域レーダーです。
ノイズは外部源によっても生成され、最も重要なのは、対象の周囲の背景の自然熱放射です。現代のレーダーシステムでは、内部ノイズは通常、外部ノイズと同等か、それ以下です。例外は、晴れた空に向けられたレーダーで、シーンが「冷たい」ため、非常に少ない熱ノイズしか生成しない場合です。熱ノイズ電力は kB T B で与えられ、T は温度、B は帯域幅(マッチドフィルター後)、kB はボルツマン定数です。
ノイズはランダムであり、対象信号はそうではありません。信号処理は、この現象を利用して、ノイズフロアを低減できます。移動目標指示と共に使用される信号積分は、積分するパルス数をNとすると、SN比を√N倍改善できます。信号は、パルスドップラー信号処理のために複数のフィルターに分割することもでき、これによりドップラーフィルタバンクによる処理で特定の速度帯のクラッタ(不要反射)を抑制し、信号対クラッタ比を改善します。これらの改善は、コヒーレンスに依存します。
干 渉
概 要
レーダーシステムは、注目する対象に焦点を当てるために、不要な信号を区別しなければなりません。これらの不要な信号は、内部および外部の、パッシブおよびアクティブな両方の源から発生する可能性があります。レーダーシステムがこれらの不要な信号と区別する能力は、その信号対雑音比(SNR)によって定義されます。SNRは、所望の信号内の信号電力と雑音電力の比として定義され、所望の目標信号のレベルと背景雑音(大気雑音および受信機内で生成される雑音)のレベルを比較します。システムのSNRが高いほど、実際の目標と雑音信号を識別する能力が高くなります。
クラッター
クラッターは、レーダー操作者にとって興味のない対象(目標でない物)から返される無線周波数(RF)エコーを指します。そのような対象には、建物などの人工物や、チャフなどのレーダー対策、地面、海、降水、雹、粉塵嵐、動物(特に鳥)、大気循環の乱れ、流星の軌跡などの自然物が含まれます。レーダークラッターは、地磁気嵐やその他の宇宙天気現象によって電離圏に生じる擾乱などの他の大気現象によっても引き起こされます。
クラッターは、レーダー送信機とアンテナ間の長いレーダー導波管によっても引き起こされる可能性があります。回転アンテナを持つ一般的な平面位置表示(PPI)レーダーでは、受信機が導波管内の塵の粒子や誤った無線周波数からのエコーに応答するため、通常、表示の中心に「サンバースト」として現れます。送受信機のスイッチングタイミング調整によって、通常、サンバーストはアンテナに近い位置での反射や漏洩信号によって引き起こされるため、範囲の精度に影響を与えることなくサンバーストを低減できます。
クラッターは、レーダー信号に応答してのみ現れるため、パッシブな反射源と見なされます。
クラッターは、いくつかの方法で検出され、中和されます。クラッターは、レーダースキャン間でほぼ同じ位置に現れる傾向があります。後続のスキャンエコーでは、所望の目標は移動しているように見え、すべての固定物体からのエコーを排除できます。海のクラッターは水平偏波を使用することで低減でき、雨は円偏波で低減されます。その他の方法としては、信号対クラッター比を増加させることが挙げられます。
クラッターは風と共に移動するか、静止しています。クラッター環境での性能測定を改善するための2つの一般的な戦略は次のとおりです。
- 移動目標指示(連続するパルス間の差分を取ることで静止物体からの反射を除去します)
- ドップラー処理(フィルターを使用して所望の信号からクラッターを分離します)
最も効果的なクラッター低減技術はパルスドップラーレーダーです。ドップラーは、周波数スペクトルを使用してクラッターを航空機や宇宙船から分離し、同じ空間内に存在する複数の反射体からの信号を、それらの速度差に基づいて分離できます。このためにはコヒーレント(位相が制御された)送信機が必要です。別の技術は、移動目標指示を使用して、位相を利用して2つの連続するパルスからの受信信号を減算し、低速移動物体からの信号を低減します。これは、コヒーレントな送信機を持たないシステム(時間領域パルス振幅レーダーなど)に適応できます。
一定の偽警報率(CFAR)は閾値設定の手法であり、自動利得制御(AGC)とは関連していますが異なります。CFAR は、周囲のクラッターレベルに対して、注目する目標からのエコーを識別するための方法です。受信機の利得は、全体の可視クラッターを一定のレベルに保つように自動的に調整されます。これは強い周囲のクラッターに埋もれた目標の検出には直接役立ちませんが、強い目標源を区別するのに役立ちます。過去には、レーダーAGCは電子的に制御され、レーダー受信機全体の利得に影響を与えていました。レーダーの進化に伴い、CFARはコンピュータソフトウェアで制御され、特定の検出セルでより細かい粒度で閾値に影響を与えるようになりました。
クラッターは、地面の反射、大気ダクティング、または電離圏の反射/屈折(異常伝搬など)による有効な目標からの多重経路エコーからも発生する可能性があります。この種のクラッターは特に厄介で、他の通常の点目標と同じように移動し、振る舞うように見えます。典型的なシナリオでは、航空機のエコーが下の地面で反射され、受信機には正確なものの下に同一の目標として現れます。レーダーは目標を統一しようとし、目標を不正確な高度で報告するか、信号の揺らぎや物理的に不可能な動きに基づいて偽目標として排除します。
地形反射妨害は、電子妨害装置が意図的に地形を利用して反射させることでレーダーを混乱させる技術です。これらの問題は、レーダーの周囲の地図を組み込み、地面の下または特定の高度の上に見える全てのエコーを排除することで克服できます。モノパルスは、低仰角で使用される仰角アルゴリズムを変更することで改善できます。最新の航空交通管制レーダー機器では、アルゴリズムを用いて現在受信したパルスを隣接パルスと比較し、エコーの統計的特性を分析することで、偽の目標を識別します。
妨 害
レーダー妨害は、レーダーの外部にある源から発生する無線周波数信号で、レーダーの周波数で送信し、注目する目標を隠すことを指します。これはアクティブジャミングとも呼ばれます。妨害は、電子戦術などの意図的なものや、同じ周波数範囲で送信する装置を操作する友軍部隊などの非意図的なものがあります。妨害は、レーダー信号とは一般に無関係なレーダーの外部の要素によって開始されるため、アクティブな干渉源と見なされます。
妨害はレーダーにとって厄介ですが、レーダーの使用目的を考えると、妨害が試みられることは容易に想像できます。妨害信号は一方向(妨害機からレーダー受信機へ)のみを移動する必要があるのに対し、レーダーエコーは二方向(レーダー → 目標 → レーダー)を移動し、そのため逆四乗則に従ってレーダー受信機に戻る際に電力が大幅に減少するためです。したがって、妨害機は妨害されるレーダーよりもはるかに低出力でも、妨害機からレーダーへの視線上の目標を効果的に隠すことができます(メインローブ妨害)。
また妨害機は、レーダー受信機のサイドローブを通じて異なる方向にあるレーダーにも影響を与えることがあります(サイドローブ妨害)。
メインローブ妨害は、通常、メインローブの立体角を狭めることによってのみ低減でき、レーダーと同じ周波数と偏波を使用する妨害機に直接直面する場合は完全に排除できません。サイドローブ妨害は、レーダーアンテナ設計における受信サイドローブを低減し、全方向性アンテナを使用してメインローブ以外の信号を検出し、無視することで克服できます。その他の対妨害技術として、周波数ホッピング、偏波の変更、ECCM[ electronic counter countermeasure] 対電子対策 (敵の実施する電子戦を排除し、味方の電磁波の効果的使用を確保するためにとられる活動)、適応型ビーム形成などがあります。
信号処理
距離測定・移動時間
距離測定(測距)の一つの方法は、飛行時間に基づいています:短い無線信号(電磁放射)のパルスを送信し、反射して戻ってくるまでの時間を測定します。距離は、往復時間の半分に信号の速度を掛けたものです。1/2の係数は、信号が対象物まで往復する必要があるためです。無線波は光速で移動するため、正確な距離測定には高速の電子機器が必要です。
ほとんどの場合、受信機は信号送信中に帰ってくる電波の信号を検出しません。サーキュレータやデュプレクサを使用することで、レーダーは事前に決められたタイミングで送信と受信を切り替えます。同様の効果により、最大範囲も制限されます。範囲を最大化するためには、パルス間の時間を長くする必要があり、これはパルス繰り返し時間、またはその逆数であるパルス繰り返し周波数と呼ばれます。
これら2つの効果は互いに相反する傾向があり、1つのレーダーで短距離と長距離の両方の性能を両立させるのは簡単ではありません。これは、良好な最小範囲に必要な短いパルスのエネルギーが少なく、帰ってくる電波の信号が小さくなり、対象物の検出が困難になるためです。これは、より多くのパルスを使用することで相殺できますが、それは最大範囲を短縮することになります。そのため、各レーダーは特定のタイプの信号を使用します。長距離レーダーは、長いパルスと長い遅延を使用し、短距離レーダーは小さいパルスと短い間隔を使用します。
電子機器の改善により、多くのレーダーは現在パルス繰り返し周波数を変更でき、範囲を変えることができます。最新のレーダーはスタガードPRF[Pulse Repetition Frequency](パルス繰り返し周波数)や多重PRF技術を用いて、1つのセル内で複数のパルスを発射し、短距離用(約10 km)と長距離用(約100 km)の別々の信号を使用します。
距離は時間の関数としても測定できます。レーダーマイルは、レーダーパルスが1海里を移動し、対象物で反射して、レーダーアンテナに戻るまでの時間です。1海里は1,852メートルと定義されているため、この距離を光速(299,792,458 m/s)で割り、結果に2を掛けると、12.35マイクロ秒の持続時間となります。
周波数変調
距離測定レーダーのもう一つの形式は、周波数変調に基づいています。これらのシステムでは、送信信号の周波数が時間とともに変化します。信号が対象物まで往復するには有限の時間がかかるため、受信信号は、反射信号がレーダーに戻ってくる時点で送信機が放送している周波数とは異なります。2つの信号の周波数を比較することで、その差を簡単に測定できます。これは1940年代の電子機器でも非常に高い精度で簡単に達成できます。さらに利点として、レーダーは比較的低い周波数で効果的に動作できます。これは、高周波信号の生成が難しいか高価だった初期の開発において重要でした。
この技術は連続波レーダー、特にFMCW(Frequency-Modulated Continuous Wave)レーダーで使用され、航空機のレーダー高度計や現代の自動車用レーダー、産業用センサーによく見られます。これらのシステムでは、「キャリア」レーダー信号が予測可能な方法で周波数変調され、通常、オーディオ周波数で正弦波または鋸歯状パターンで上下に変化します。信号は1つのアンテナから送信され、通常は航空機の下部にある別のアンテナで受信され、送信信号の一部と返された信号を簡単な周波数ビート変調器で継続的に比較できます。
受信信号上の変調指数は、レーダーと反射体の間の時間遅延に比例します。周波数シフトは時間遅延が大きいほど大きくなります。周波数シフトは移動距離に直接比例します。その距離は計器に表示でき、トランスポンダを介して利用可能な場合もあります。この信号処理は、速度検出ドップラーレーダーで使用されるものに似ています。このアプローチを使用するシステムの歴史的な例として、AZUSA、MISTRAM、UDOPがあります。
地上レーダーは、より広い周波数範囲をカバーする低出力FM信号を使用します。複数の反射は数学的に分析され、SAR(合成開口レーダー)やISAR(逆合成開口レーダー)の原理を用いて複数のパスでコンピューター合成画像を作成します。ドップラー効果が使用され、低速で移動する物体を検出でき、水面からの「ノイズ」をほぼ完全に排除できます。
パルス圧縮
上記の2つの技術はそれぞれ欠点があります。パルスタイミング技術には、距離測定の精度がパルスの長さに反比例するという固有のトレードオフがあり、エネルギーと方向範囲は直接関係しています。長距離のための電力を高めながら精度を維持するには、非常に高いピークパワーが必要で、1960年代の早期警戒レーダーはピーク電力で数十メガワットで動作することがよくありました(平均電力はずっと低い)。連続波方式はエネルギーを時間に分散させるため、パルス技術と比較してはるかに低いピークパワーが必要ですが、送信と受信信号を同時に動作させる方法が必要で、多くの場合2つの別々のアンテナを必要とします。
1960年代の新しい電子機器の導入により、2つの技術を組み合わせることができました。まず、周波数変調された長いパルスから始まります。送信エネルギーを時間に広げることで、低いピークエネルギーを使用でき、現代の例は通常ピーク電力で数十キロワットのオーダーです。受信時、信号は異なる周波数を異なる時間だけ遅延させるシステムに送られます。結果として得られる出力は、正確な距離測定に適した、はるかに短いパルスであり、同時に受信エネルギーをはるかに高いエネルギーピークに圧縮し、信号対雑音比を向上させます。この技術は現代の大型レーダーでほぼ普遍的になっています。
速度測定
速度とは、時間に対する対象または目標までの距離の変化です。したがって、距離を測定する既存のシステムに、目標の前回の位置を記憶する能力を組み合わせることで、速度を測定できます。かつては、ユーザーがレーダー画面に油性の鉛筆(日本ではダーマトグラフが一般的)で印をつけ、そしてスライド定規を使用して速度を計算することでした。現代のレーダーシステムは、コンピューターを使用してこの同等の操作をより速く、より正確に実行します。
「送信機の出力が位相同期(コヒーレント)である場合、ドップラー効果として知られている、ほぼ瞬時の速度測定が可能になる別の効果があります。ほとんどの現代のレーダーシステムは、このドップラーレーダーおよびパルスドップラーレーダーシステム(気象レーダー、軍事レーダー)の原理を使用しています。ドップラー効果は、レーダーから目標への視線に沿った目標の相対速度(レンジレートまたは視線速度とも呼ばれる)のみを決定できます。目標の速度の視線に垂直な成分は、ドップラー効果だけでは決定できませんが、時間とともに目標の方位角を追跡することで決定できます。
パルスを使用せずに、既知の周波数の非常に純粋な信号を送信することで、ドップラーレーダーを作ることも可能です。これは連続波レーダー(CW [continuous-wave] レーダー)と呼ばれます。CWレーダーは、目標の視線に沿った速度成分を決定するのに理想的です。CWレーダーは、通常、範囲が重要でない場合に、車両の速度を迅速かつ正確に測定するために交通取り締まりなどで使用されます。
パルスレーダーを使用する場合、連続する反射波の位相の変化により、パルス間で目標が移動した距離が分かり、したがってその速度を計算できます。現代のレーダーでは、MTI(Moving Target Indication)やMTD(Moving Target Detection)などの信号処理技術も広く使用されています。レーダー信号処理におけるその他の数学的手法には、時間-周波数分析(ワイル代数・ハイゼンベルク代数・ウェーブレット解析)や、移動する目標からの反射波の周波数変化を利用するチャープレット変換などがあります。チャープレットは特にマイクロドップラー解析や複雑な目標識別に特に有用です。
宇宙ロケット追跡システム:AZUSA、MISTRAM、UDOP
多点式レーダーシステム(Multi-Static Radar System: MSRS)は、ロケットやミサイルの軌道を高精度で追跡・測定するために開発された地上レーダー追跡システムの総称です。これらのシステムは主に1950年代から1970年代にかけて米国で開発・運用され、共通の特徴として、観測対象に搭載された応答機(トランスポンダー)と地上の送信局、そして正確に配置された複数の受信局を組み合わせて使用します。代表的なMSRSとして、AZUSA、MISTRAM、UDOPなどがあります。
AZUSA(アズサ)は、1950年代中頃からフロリダ州ケープカナベラルとNASAケネディ宇宙センターに設置された地上レーダー追跡システムです。この名称は、システムが考案されたカリフォルニア州南部の町アズサに由来しています。AZUSAはCバンドの連続波(CW)干渉計方式を採用しており、1台の送信機と、2本の交差した基線に沿って配置された9台の受信機(全長約500メートル)で構成されています。測定方法としては、搬送波を変調する側波帯周波数の位相測定、ドップラーカウントによる整合性のある距離測定、2つの方向余弦およびその変化率を利用します。通常の運用範囲内での精度は距離誤差3メートル(9.8フィート)未満、方向余弦で20 ppm(100万分の20)の誤差とされています。AZUSAの特徴として、5〜50メートル間隔で配置された中間受信機により、位相の多義性を解決する仕組みが採用されています。
MISTRAM(MIssile TRAjectory Measurement)は、1960年代にアメリカ空軍が開発し、後にNASAも採用した高解像度の追跡システムです。このシステムは連続波技術により従来のパルスレーダーの限界を克服しました。MISTRAMは連続波(CW)干渉計システムを採用しており、フロリダ州バルカリアとバハマのエルーセラ島に設置された地上局と、3〜30 km間隔で2本の直交する基線に沿って配置された受信局で構成されています。このシステムはターゲットの距離、4つの距離差、距離率、および4つの距離差率を測定する能力を持っています。動作原理としては、Xバンドの無線周波数搬送信号を送信し、ロケットのトランスポンダーがシフトした周波数で再放送するというものです。搬送周波数をゆっくり変更し、返信信号の位相と比較することで高精度な測定を実現しています。実際の運用範囲内では0.8メートル(2.6フィート)未満の距離誤差という高精度を実現し、理論上は月までの距離でも1 km未満の精度を持つとされていました。MISTRAMは1960年代から1970年代まで運用されました。
UDOP(Ultra-high-frequency Doppler)は、ドップラー効果を利用したマルチスタティックレーダーシステムで、他のシステムと比較して比較的低コストで高精度な測定を実現しました。UDOPは超高周波(UHF)ドップラーレーダー技術を採用しており、ターゲットに450 MHzの信号を照射し、基線に沿って40〜120 km間隔で配置された5つの受信局がトランスポンダーから900 MHzの信号を受信するという構成になっています。このシステムは5つの受信局からの斜距離速度データを生成しますが、距離や位置の計算には他の追跡システムからの初期位置情報が必要です。標準的な運用条件下での偶然誤差は6センチメートルとされていますが、総合誤差には2.7メートルの系統誤差と初期位置に起因する誤差が含まれています。
UDOPはジェミニ計画ミッションのためのサターンロケットに搭載されたAN/DRN-11トランスポンダーとの連携など、米国空軍東部テストレンジ(フロリダ本土からインド洋まで)でのミサイル軌道の精密測定に広く使用されました。
これらのMSRSが開発される以前の追跡技術であるパルスレーダー技術(1950年代以前)は、無線信号がターゲットまで往復する時間を計測する方式で、精度は約1%に制限されていました。この制限の主な原因は、鋭い無線「パルス」を作成する技術的限界と、高精度時計が普及する前の時間計測の不正確さにありました。AZUSA、MISTRAM、UDOPなどのMSRSは、これらの制限を克服するために連続波技術や干渉計技術、ドップラー効果などを組み合わせた革新的なアプローチを採用しました。これにより、ロケット打ち上げやミサイル飛行の軌道解析において飛躍的な精度向上を実現し、米国の宇宙開発・ミサイル開発プログラムに大きく貢献しました。
各システムは1970年代後半から1980年代にかけて、より高度なGPS技術やレーザー測距技術などに徐々に置き換えられていきましたが、その技術的遺産は現代の宇宙追跡システムの基盤となっています。
レーダー関連を詳しくまとめました。
UTMとATC (航空交通管理) の現状と将来の展望 ATCの話1ADS-B ADS-C ADSの概要 航空管制と人口衛星 ATCの話2
ADS-Bを受信するフライト追跡表示サービス 航空機のリアルタイム運行状況 ATCの話3
空中衝突防止装置・航空機衝突防止装置 TCAS / ACAS ATCの話4
有人・無人航空機 統合運航技術 衝突回避技術・リアルタイム管制 ATCの話5